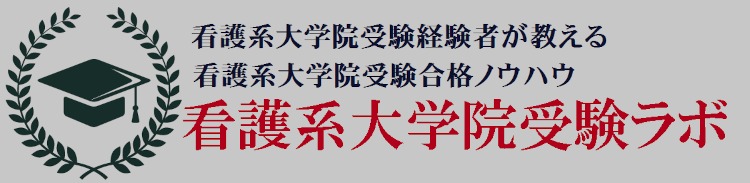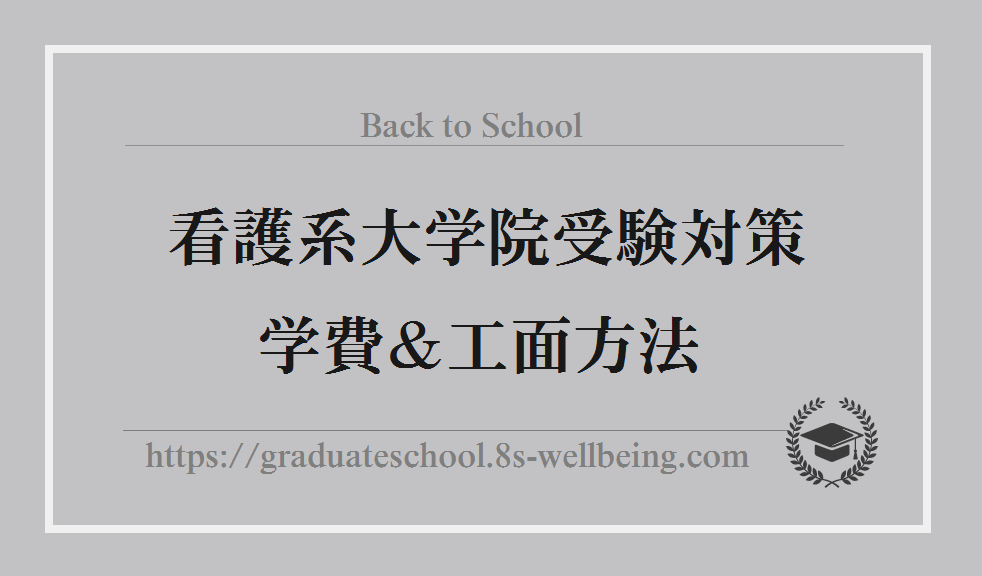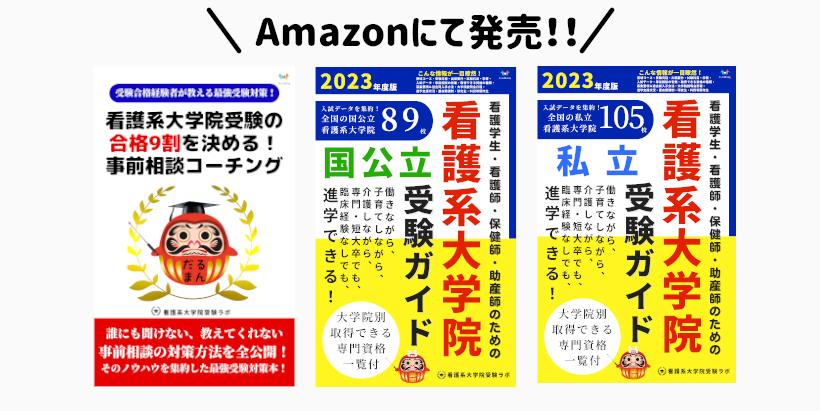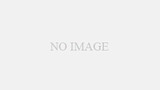大学院の学費とその工面方法をご紹介します。
学費

学費の安さは国立>公立>私立の順で安いです。しかし、最近は国立の学費が高騰化しており、そこまで安いとは言えなくなってきているようです。
具体的な金額をみてみましょう。一年目の学費▼(2020年時点)
| 区分 | 入学金 | 学費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| A 国立大学大学院 | 28万2,000円 | 53万5,800円 | 81万7,800円 |
| B 公立大学大学院 | 39万3,426円 | 53万7,809円 | 93万1,235円 |
| C 私立大学大学院 | 40万円 | 120万円 | 160万円 |
募集要項に掲載されている学費から、課程ごとの概算を出してみました。
| 区分 | 課程 | 合計 |
|---|---|---|
| 国公立 | 修士(2年) | 1,353,600円 |
| 国公立 | 博士(3年) | 1,889,400円 |
| 私立 | 修士(2年) | 2,800,000円 |
| 私立 | 博士(3年) | 4,000,000円 |
学費の工面の仕方

学費の工面方法をご紹介します。
入学前に貯蓄
社会人時代の貯蓄で賄う場合もあれば、1年程度計画的に学費貯金をしてから受験される方もいます。
入学後はアルバイトをする時間が取れないと見積もって、生活費まで見込んで準備している方もいました。
アルバイトは出来ますが、実際には学業に忙しくなるため、まずは、2年程度の学費と生活費を確保しておくと精神的にも負担は少ないかもしれません。
大学院生のアルバイトの限度についてはこちら▼
親・家族からの経済的支援
親や家族から支援をしてもらう方もいます。出世払いでとのことで家族から快い応援を頂いていました。
奨学金制度を利用する
大学院生も利用できる奨学金制度が3種類あります。
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)
国の機関「独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)」です。
貸与型で第1種(無利子)と第2種(利子有)があります。それぞれ条件がありますので、詳しくはJASSO公式HPをご覧ください。
学校法人主催の奨学金制度
学校法人ごとに行っている奨学金制度があります。
多くは「給付型」なので、返済義務がありません。そのため、応募条件が厳しかったり、応募の倍率が高い傾向にあります。
学校法人ごとにそのような類の奨学金制度の保有状況は異なるため、学生支援課へお問い合わせください。
民間団体主催の奨学金制度
民間の団体が開催している奨学金制度です。
こちらも「給付型」が多く、人気があります。応募要件(専攻・地域・出身地・課程・資格等)を指定している場合が多く、看護・医療系で応募できる奨学金制度は多いほうではないです。
情報収集は、ネットでも出来ます。「奨学金.net」という奨学金に関する情報を掲載しているサイトがあります。よろしければ、ご覧ください。
もしくは、大学院の学生支援課窓口にて相談することも出来ます。窓口では、民間の奨学金制度の募集要項をファイリングしており、閲覧をさせてくれます。
地方公共団体奨学制度
国公立系大学大学院の場合、上記にご紹介した奨学金以外に、地方公共団体が行っている奨学金制度があります。
大学院公式HPに「奨学金制度」の案内ページがありますので、各大学院の公式HPをご覧ください。
在職のまま社会人入学
文部科学省の方針により、社会人の大学院進学を推奨され、在職のまま大学院へ進学することができる制度が出来ました。
ただし、看護系大学院の場合は基本的に「論文コース」のみを対象とし、臨床実習を要する保健師・助産師・CNS等の受験資格取得コースは対象外となっています。
詳しい制度は「社会人受け入れ推進方策」をご覧ください。今のところ、下記の3制度を多くの大学院で採用しています。全大学院ではありませんので、詳しくは受験大学院へお問い合わせください。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 社会人試験 | 試験項目が少ない、配点の配慮 |
| 昼夜開講制度 | 平日の夜間、土曜日・日曜日、夏季・冬季等の休業期間中などに授業を開講 |
| 長期履修制度 | 修学期間の延長(法人により限度あり) |
まとめ
以上、大学院の学費と工面方法のご紹介でした。何かと方法はあります。学費は決して安くありませんが、それ以上に得られるものは多いと思います。ぜひ、これらの情報を踏まえて、大学院へ一歩踏み出してみては如何でしょうか。

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。次は「大学院卒業後の進路」についてです♪