こんにちは、だるまんです。
大学院受験では、決まって、願書出願前に志望校の教授とマンツーマンでの進学相談、いわゆる、事前面接(研究室訪問)があります。
その事前面接(研究室訪問)では、当然ながら、大学院進学後に取り組みたい研究テーマについて話すこととなります。
自分なりに事前準備をして、事前面接に取り組んだところで、志望校の教授から良い反応や良いコメントをもらえたら何よりのことですが、真逆に、思いもよらぬ反応、意外なコメント、回答に困る質問をされ、予想外な展開に、頭が真っ白になることも多いにあります。
事前に、そのような質問があると、心の準備をしておくのと、そうではないとでは、物事の成り行きは、大いに変わってきます。
今回は、経験を踏まえて、聞かれて困る質問事例と困る質問の答え方についてお話しします。
言葉につまる質問&答え方

1.その研究に意味がありますか?
提示した研究テーマの内容に渋い反応を示され、「その研究に意味がありますか?」と聞かれたとしたら、どう答えますか?
これは、冷静に考えれば、答えようのない、代表的な質問のひとつです。
物事に意味があるかどうかは、時代によって、環境によって、相手によって、その付加価値は変わるものですが、権威ある教授から一言こういわれると、その困る質問に一瞬ヒヤッとして、何を答えたらいいのかわからなくなりがちです。
こういう答えようのない困る質問をされた時は、めげずに、「意味はあり、必要だと思って、この研究テーマを考えています。」と、堂々と自分の意思をぶれさせないこと、困る質問に触れまわされないことです。
先生の反応に、つい、「意味はないですか…」と萎縮するのではなく、自分の意見はしっかりと伝える、時に反論できること、困る質問の答え方ができるのも、先生に見られる魅力のひとつです。
思えば、この質問に深い意味はない、あなたの反応を試されていることもありえるからです。
2.それは、あちらの研究室の方がいいのでは?
やんわりと「この研究なら、うちよりも他の分野のほうがいいのでは?」と、わけわからないことを言われることがあります。
自分の母なら、口答えしてもよい領域ですが、そうはいかず…。
ニュアンスとして、やんわりお断りされているようにも感じ、気後れしそうになりますが、ここでそれを受け入れてはいけないのです。
そういう時は「ぜひ、先生からご指導を受けて研究に取り組みたいです。」と、先生の門下生として研究を取り組みたいという進学への熱意で、困る質問に答えることです。
杖の下に回る犬は打たれぬ、です。
研究というのは、意外と、その先生の専門分野でなかったとしても、先生の関心さえひけば、受け入れ可能とする場合も大いにあるからです。
常頃、芸人のネタ探しをするのも、商人が商材探しをするのも、研究者が研究材料を探すことに差はないということです。
3.フィールドがねぇ…
このコメントは、研究内容はいいのだけれど、先生にはその研究ができる研究フィールドを持っていない、ということを意味しています。
このコメントは、入学お断りに受け取りやすいですが、実際には、研究できるだろうかという、老婆心であることの方が大きいです。
ここまで具体的に憂いしているということであり、かえって入学許可というニュアンスが伺えます。
大学院生の研究活動には、研究フィールド探しが欠かせないです。
既に、研究フィールドがあるならいいのですが、フィールドがない場合、教授の研究フィールドを借りたり、教授のネットワークで協力を得ることもあります。
かえって、教授にとっても、差し当たれるフィールドがない場合もあることを先立って憂いしているのです。
この点については、教授に頼らず、協力依頼できそうなフィールドがある、ネットワークがあるという条件を持っていると強みになれますが、ないなら、進学後に自ら新規開拓をするという積極的な意思を伝えることです。
4.研究デザインはどう思っているの?
「研究デザインは、どう考えていますか?インタビューとか?それとも量?質?」と、意味不明、日本語?と思うような単語を羅列されてパニックになります。
そもそも論で、そのような研究について困る質問をされて、それに滞りなく、対等に答えられるのは、博士課程進学者もしくは臨床で看護研究キャリアを積んだ方々です。
大学院進学者の大半は、せめて大学の卒論での看護研究経験のみであるか、臨床での看護研究経験が一つあるかどうかですが、それも本格的な研究というよりは、職場内での課題レベルであったりで、看護研究に詳しくない方の方が、圧倒的に多いです。
その知識を学びに行くのが大学院であり、そのことも教授は把握しています。
にも拘わらず、自分のキャリアにはふさわしくないレベルの困る質問をされた時に、素直に「勉強不足でわかりません」「素人だからわからない」で通ったのは昔の話です。
今は、「今はわからないけれど、これから学んで、わかるようにしていく」のニュアンスで、困る質問に賢い答え方をすることです。
わかったふりをして意味不明なことをいうよりも、「わからないことはわからない」という潔さと「これから学んでいきます」というstudyではなく、learnの姿勢を魅せることも面接では、勝ち組になるテクニックのひとつです。
教授の反応をどう解釈する?

このように、自分が用意していなかった予想外な困る質問がしばしば飛んでくることがあります。
ここはあくまで私見ですが、集めた情報によると、割合的には10の質問中、3は困る質問です。
その困る質問の本意はなんなのかを、必ず、面接後に振り返ってみてください。
冷たい言葉に聞こえて、実は入学許可を意味するメッセージだったのか、心配を装って遠回しな入学お断りのメッセージだったのか…
それをキャッチすれば、安全線での受験になりそうなのか、他を検討すべきなのかの判断がつきます。
気を揉むことではありますが、これも大学院受験生として、通らなければならない成長痛のひとつです。
まとめ
これをふまえて、徹底して事前準備をしておくことです。
咄嗟に聞かれた困る質問に、どのような答え方をするのかを教授はみています、ここにあなたの本音が出るからです。
教授に困る質問をされたら、それになびかれるのではなく、何事にもぶれない自分の見解をもって臨んでください。
教授もそれを求めています。
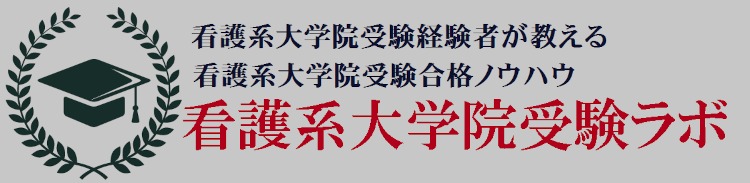

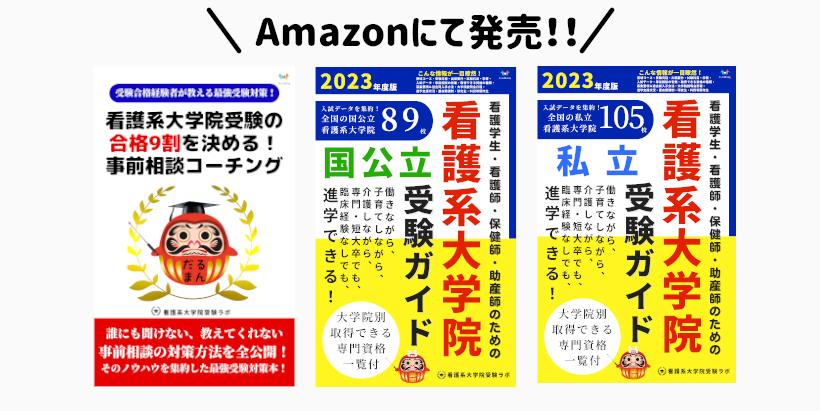



質問:「この研究に意味がありますか?」
正解:「意味はあり、必要だと思っています。」