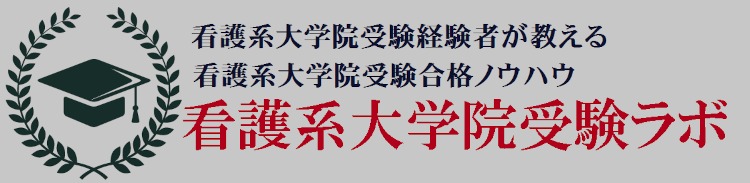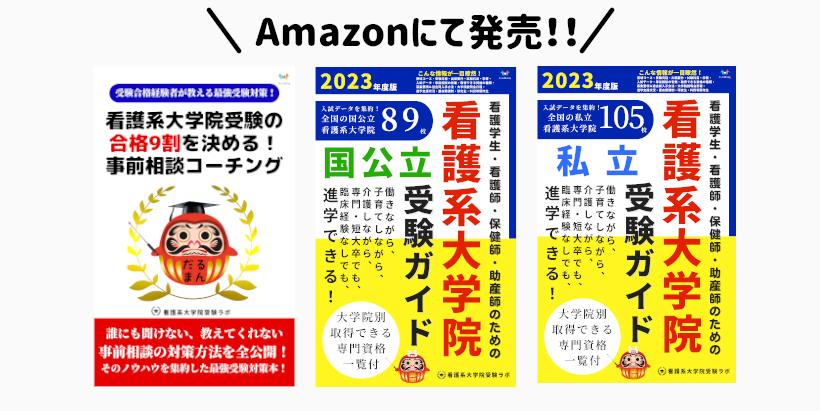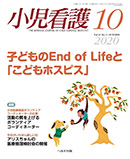こんにちは、だるまんです。
今回は、小児・小児専門看護師(CNS)を志望される方向けに、大学院の小論文・専門試験の過去問、受験経験者からの情報をもとに、頻出用語を抽出してみました。
用語一覧は、記事の最後に載せています。
質問形式
まず、よく出題する形式を下記に挙げておきます。
- ~の定義を説明しなさい
- ~の意義を述べなさい
- ~と~の違いを述べなさい
- ~の看護師の役割とは?
- ~の課題と対策を述べなさい
- ~を踏まえて、あなたの経験を述べなさい
- 必要な看護を述べなさい
小児看護学の出題傾向
小児看護学専攻の試験は、論文コースも専門看護師(CNS)コースも、一問一答の出題ではなく、回答用紙への自由記述を求められる試験が多い印象です。
具体的には、他領域に比較して、病態生理学や特定の疾病などが出ることは少なく、提示された用語に対して「~についてあなたが知っていることを述べなさい・説明しなさい」「この概念とあなたの考える看護を述べなさい」、または事例提示され、考えられる課題や必要とされる看護支援を記述する、という感じです。
この記述の際に、専門用語や看護理念などを用いて記述することができると、小論文としての評価も高いと思いますので、小児看護系雑誌等から、小論文に活かせそうなキーワードや経験談などを収集しておくと、役立てられるのではないかと思います。
また、深堀りするよりも、幅広い基本用語確認とその看護支援について着目した学習が必要だと思います。
CNS専攻の方は、時に、CNSの役割について問われることがありますので、下記のような雑誌から知識の情報収集もしておくとよいと思います。
試験対策用語
抽出した単語の中から特に頻出の10点と、その回答ヒントとなる資料や雑誌を紹介します。
① こどもの権利
「こどもの権利」は、頻出用語の中でも頻出のようです。
定義はもちろんのこと、「こどもの権利を守るための看護とは」と問われることがあります。
② プリパレーション
「言葉の定義を説明しなさい」「必要と考えられる看護を述べなさい」と問われることがあります。
③ 成人移行支援
慢性疾患を持つ子供の成人移行支援というテーマが度々、出題されているようです。
その際の「課題」「必要と考えられる支援」が問われることがあります。
④ 慢性疾患
慢性疾患を持つ子供の「課題」「看護支援」「こども・家族の疾病受容課程」「家族への支援」について問われることがあります。
⑤ 小児感染症
感染症にちなんで、昨年度、新型コロナ感染症が子供に与える健康課題という着眼点で出題された学校もありました。
⑥ ケア
こどものセルフケア能力や「こども・家族中心のケア(ファミリーセンタードケア)」というキーワードが着目されているようです。
「看護師として役割」について問われることがあります。
⑦ 理論
「Bowlby のアタッチメント理論」「エリクソンの発達課題」「ピアジェによる感覚運動器」など、理論の説明を問われることがあります。
⑧ 児童虐待
「児童虐待の社会の背景」「看護師の役割」について問われることがあります。
⑨ チーム医療
近年、チーム医療、多職種連携という言葉がキーワードになってきています。
記述する際に織り込めるキーワードとしても使えると思います。
⑩ 入院・退院支援
「入院する子供の不安についての説明」、「家族への支援」について問われることがあります。
この時に、自我発達理論、分離不安、コーピングといった用語を用いて説明できると尚よいようです。
用語一覧
用語一覧はこちらです。
まとめ
小児看護試験は、「定義」と「看護の役割・支援」について着目して学習することがポイントだと思います。
小児看護雑誌のバックナンバーにあるタイトルは、今回抽出した単語とリンクしているものが多かったです。
バックナンバーのタイトルや目次を見るだけでもかなり参考になると思います。
富士山マガジンで「小児看護」の定期購読(送料無料、増刊号1冊付)
試験日が刻々と迫る中、小論文や専門試験はどのような対策をしたらいいのか、今の学習方法で良いのだろうか、戸惑いがちですが、イチロー選手の言葉を借りれば、「壁というのは、出来る人にしかやってこない。超えられる可能性のある人にしかやってこない。だから、壁があるときはチャンスだと思っている。」です。
必ず、超えられる壁です。
自分が自分を一番に信じてあげること、壁の向こうにある世界があなたを待っています。