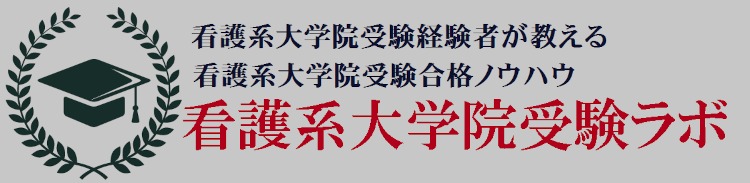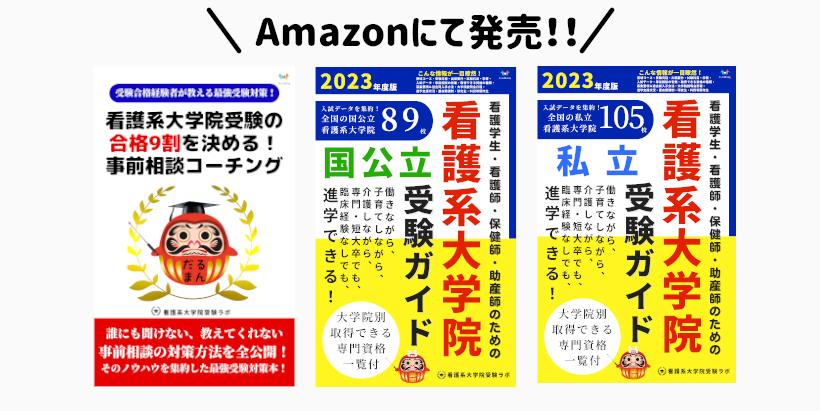こんにちは、だるまんです。
今回は、母性・助産学・母性専門看護師(CNS)を志望される方向けに、大学院の小論文・専門試験の過去問、受験経験者からの情報をもとに、頻出用語を抽出してみました。
全部で78用語ある中で、特に大事だと思われる用語10点を抽出して解説します。
最後に78用語一覧を載せています。
質問形式
まず、よく出題する形式を下記に挙げておきます。
- ~の定義を説明しなさい
- ~の意義を述べなさい
- ~と~の違いを述べなさい
- ~の看護師の役割とは?
- ~の課題と対策を述べなさい
- ~を踏まえて、あなたの経験を述べなさい
- 必要な看護を述べなさい
母性看護学の出題傾向
母性関連の制度、理論、妊娠・出産・産褥期ケア、性感染症、性教育、避妊、地域連携、産婦人科系疾病、更年期障害、新生児ケア等など、他分野と比較して、出題範囲の幅がかなり広いという、私見です。
志望コース別に下記のような出題傾向はあるようです。
母性看護学では、「定義」「課題」「看護師の役割」などの問いが多いようです。
助産学は、看護国家試験問題のような一問一答の病態生理学的問題、事例問題からアセスメントを行う問題が多いようです。
母性専門看護師(CNS)の場合は、事例が出題され、具体的に考えられる看護の課題や看護計画、病態の知識が問われる問題が多いです。
試験対策用語
① リプロダクティブヘルス・ライツ
「リプロダクティブヘルス・ライツ」は、「定義・概念」「課題」「支援」について問われることがあるようです。
② 健やか親子21
近年、社会問題となっている「子供の虐待」に関連して、健やか親子21の重要課題②「妊娠期からの児童虐待防止対策」が問われることがあるようです。
他にも、基本課題A・B・Cにある課題をふまえて、グラフからわかることを問われたり、取り組みについて問われることもあるようです。
③ 合計特殊出生率
合計特殊出生率は、「定義」「課題」などが、度々試験にでるようです。
合計特殊出生率とセットで「人口置換水準」も覚えておくとよいと思います。
④ 少子化
少子化の課題と取り組みについて問われることがあるようです。
このような問いには、「少子化社会対策大綱」の取り組みを適用させることです。
⑤ 連携
母性領域では、状況により、妊産婦や乳幼児の支援のため、都道府県・市区町村(児童相談所)、福祉事務所(家庭児童相談室)、保健所・市町村保健センター、発達障害者支援センター等などあらゆる関係機関と連携することが必要な場合があります。
近年、他看護分野でも「連携」という言葉はキーワードとなっていますので、これもチェックしておきたい用語です。
⑥ 産後うつ・マタニティブルーズ
「産後うつの概要」、「産後うつの女性に対して必要な看護」、「マタニティブルーズとの違い」について問われることがあるようです。
⑦ 新生児蘇生
事例が提示され、「積極的新生児蘇生が必要かどうか」、「どのような判断で蘇生をするのか」を問われることがあるようです。
⑧ 更年期障害
更年期障害の発症要因、症状、治療などの身体的な面、精神的な面、それに必要と考えられる看護について問われることがあるようです。
⑨ 妊娠合併症
「糖尿病合併妊娠」「妊娠高血圧症候群」「乳腺炎」「妊娠糖尿病」「浮腫」「便秘」等、妊娠中のトラブルや合併症などの病態生理やそれに必要な看護支援が問われることがあるようです。
⑩ 出産・産後ケア
さまざまな対象における妊娠出産、産褥期ケアについて、「妊産婦における課題」と「必要と考えられる看護実践・看護支援」と問われることがあるようです。
例えば、下記のような対象があげられます。
- 在日外国人妊産婦
- 高齢出産の妊産婦
- 前期破水と診断された妊産婦
- 早退妊娠および切迫早産で長期入院中の妊産婦
- 流産・死産をした母親
用語一覧
用語一覧はこちらです。
まとめ
母性看護・助産・母性専門看護師専攻の筆記試験は、かなり看護国家試験に近い出題傾向があるように感じています。
過去問から傾向を掴むこと、幅広く学習しておくこと、その際に「定義」「課題」「看護師の役割」の3点を念頭におきながら学習することが必要だと思います。
今回、抽出して載せた用語は、頻出度が高いだけでなく、使用範囲も広いので、小論文などの論述時に関連用語としても活用できる用語です。
医療従事者や関係者に限らず、一般的にも使われる用語ですので、役に立つと思います。