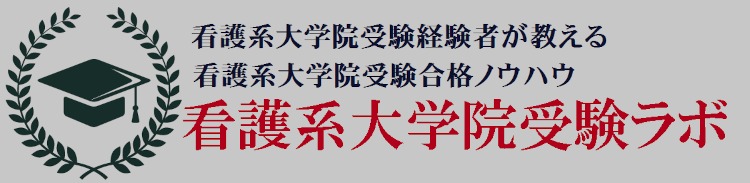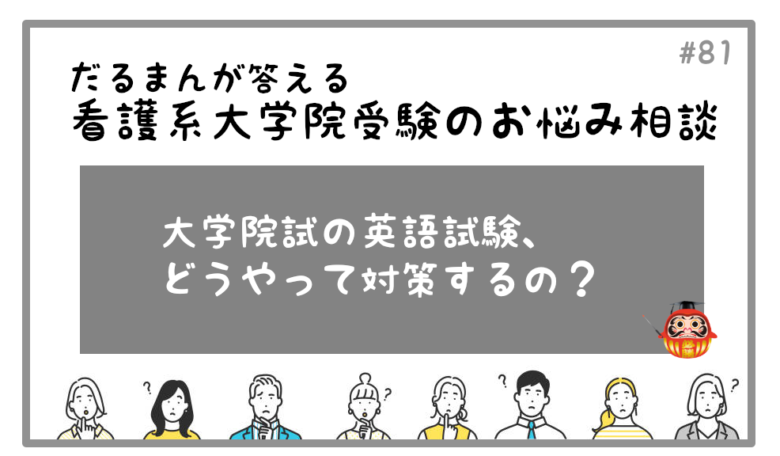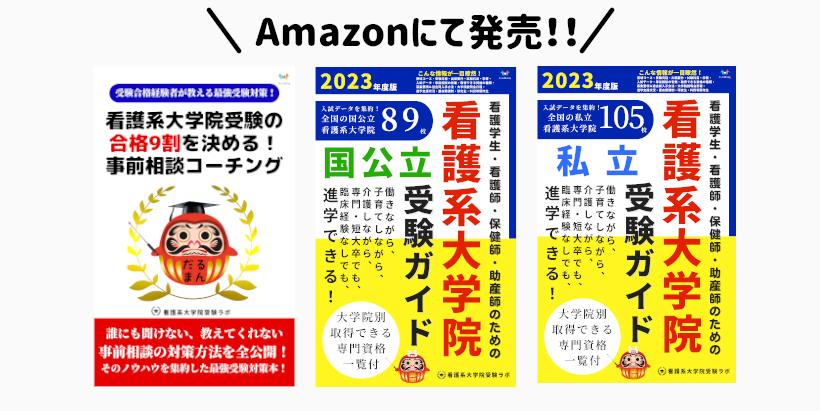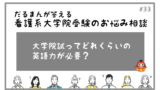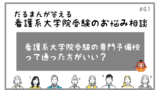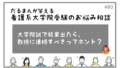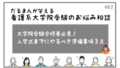こんにちは、だるまんです。
大学院入試に欠かせない試験科目となっているのが「英語」です。
新型コロナ感染症の影響により筆記試験からオンライン試験へ移行した大学院の中には、英語筆記試験の代わりにTOEICやTOEFL、英検のような外部英語スコア提出に切り替えたところもありますが、
未だ大半の大学院では、英語筆記試験を実施しています。
この英語筆記試験をどのように対策したらいいのかについて関心を持たれる受験生の方は多く、今回は、院試英語対策方法を提案させて頂きます。
大学院によって試験内容や試験傾向がありますが、大まかに共通している部分はあるので、参考にしていただければ幸いです。
質問内容

大学院入試に英語試験があります。志望先には過去問もない状況で、院生の知り合いもおらず、聞ける人もいません。英語、どのように取り組まれましたか?
だるまんの回答
院試の英語試験とは

まず、大学院入試の英語試験とはどういう試験なのかについて簡単にお話しします。
各大学院毎に出題内容や傾向はそれぞれですが、一般論で言うならば、大学院試の英語筆記試験とは、いわば、「英語長文読解」であり、
その英語長文読解の問題となる長文の出典元は、各専攻分野における英語論文となっています。
その難易度は、大学受験のように、各大学ごとに異なるものですが、
大学院受験には偏差値があるわけではないため、実際に過去問を解いてみなければ難易度はわからない、過去問さえない大学院なら難易度さえわからない、というのが現状です。
試験時間にして60分~90分で、大問2~3程度、おおまかなレベルで言うならば、国立が研究者レベル、公立・私立が大学受験レベルであると言えます。
そして、肝心な大学院試の英語の出題を見てみると、
- 「下線分を日本語訳にしなさい」
- 「代名詞が指す意味を書き出しなさい」
- 「この長文を3行以内で要約しなさい」
- 「この長文のキーワード●●についてあなたの意見を書きなさい」
というように、〇か×かの一問一答とは異なり、長文が読めれば、解ける問題であることが多く、院試は基本的に落とす試験ではないということがわかります。
なので、努力すべきことは、ただ一つ、英語長文を早く読み取れること、これに限ります。
では、どうやって訓練をしていくのか。
英語長文読解訓練方法
1.過去問を入手する
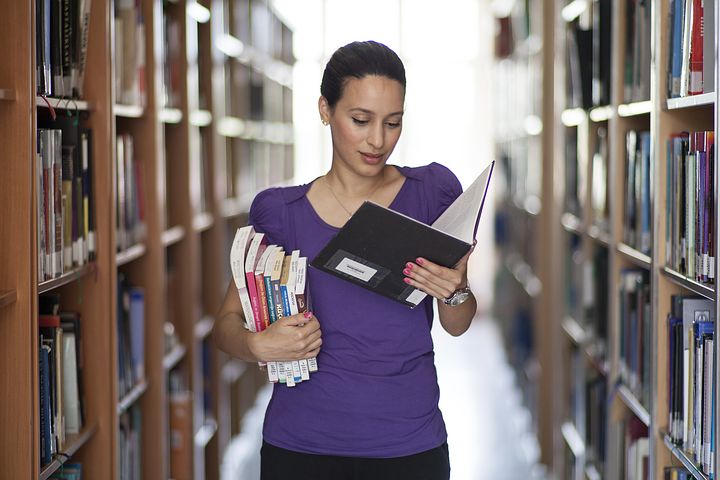
具体的には、まず、過去問を入手してください。
過去問を入手することで、
- 英語試験の難易度
- 出題長文の出典元
という2点の情報を得ることが出来ます。
そうすれば、自分と志望校の試験レベルとどれくらいの開きがあるのかを知ることができます。
ただ、残念ながら、公表されている過去問とは、過去1年~3年のみしか入手できないことが多く、解答もついていませんので、難易度や問題の出題形式や出典元は把握できますが、得られる情報はそこまでです。
では、続いて、できる対策の話を続けます。
2.英語教材を揃える
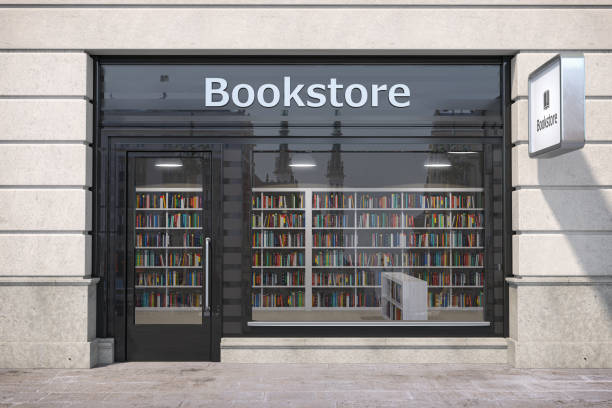
長文読解と一言に言っても、大学受験の英語とは異なり、多くの大学院、特に国公立では、実際に公表されている英語論文を長文問題として採用していることが多いです。
ということは、英語論文が読めるようになることが、最終目的になります。
英語論文というと、難しく感じられるかもしれませんが、独特な言い回しや専門用語を覚えていけば、対応することは可能なことです。
そこで筆者が提案するのは、
- 英語論文の英語を知る
- 英語論文を量で読みこなしていく
ということを同時並行で取り組んでいくということです。
英語論文の英語を知る
英語論文には、独特の言い回しやよく使う表現などがたくさんありますので、その構文パターンを覚えていくことです。
そのため、まずはその知識を身につけるために、おすすめしたいのが、こちらの書籍です。
筆者は看護系なので、院試対策に使った書籍紹介のページで、看護医療系の英語対策本はご紹介していますが、こちらの書籍であれば、分野関係なく対応できると言えます。
これに限らずとも、英語論文を読むためのノウハウが書かれている書籍があれば、ぜひ入手して受験勉強本にされることをおすすめします。
英語論文を量で読みこなしていく
いくら教科書を揃えて知識を取得したとしても、それを本番の英語長文で活用するためにも、実践の数を重ねて経験を積んでいくことです。
具体的には、CinniもしくはGoogle schoolarで英語論文を無料検索することができ、「要約」や「はじめに」あたりであればどの論文でも見れます。
一部なら全文ダウンロードもできるので、専攻分野に関する論文を印刷して、実際に翻訳をしてみることです。
もちろん、解答はないので、google翻訳にかけてみたり、パソコンの画面上で右クリック「日本語翻訳」機能で全自動翻訳等、便利なツールを活用しながら独自で学習を積み重ねて英語を訳す経験を積み重ねていくことです。
または、方法としての情報ですが、東京大学大学院では過去問を公開または販売されていますので、難易度の高い英語を参考までに解いてみるというのも、問題を解く力をつけるのに良い教材になれるかと思います。
- 東京大学大学院人文社会系研究科過去問
- 修士課程 過去問題集 – 東京大学理学部物理学科
- 東京大学大学院情報学環・学際情報学府
- 過去の試験問題 | 大学院入試情報 – マテリアル工学科
- 大学院入試(修士・博士課程)過去問題集 – 地球惑星科学専攻
- 東京大学大学院教育学研究科
- 東京大学大学院医学系研究科(東京医学会)
※他にもあると思いますが、検索できた専攻を掲載しています。
または、試験問題には直結しないですが、論文と限らずとも、長文そのものになれていく、見分を広げるがけら、News weekやTimesを購読してみるのもありだともいえます。
3.予備校に通う

独学を始めてみて自分にこの受験スタイルが合わない、時間管理が難しいという戸惑いがあるなら、潔く予備校にお世話になると言うのもひとつ方法だと言えます。
全国に数少ないながら大学院予備校がありますので、通学型なのか、通信型なのかそれぞれ検討をされてみるのもよしだと思います。
ただし、一般的に大学院予備校には、その分野専門の英語教師がいるわけではないことが多いと感じています。
要は、英語を教授した経験のある教師が講師をされていますが、大学院受験の英語試験では専門知識がなければ理解できない部分が多くあり、その辺を教えてもらうことはできない、ということがあります。
なので、予備校で一般論を教わったら、それをご自分でより踏み込んで専門分野的な理解を深める努力は必要だと思います。
まとめ
以上、「大学院試の英語試験、どうやって対策するの?」でした。
院試の核心でもある「英語」では、高スコアを取得するに越したことはないので、個々に試行錯誤しながら、どのように取り組めば英語読解力が伸びるのかを検討して、取り組んでいく必要があります。
人によって学習形式はそれぞれ、自分に合った方法を見つけ出し、自己流の受験スタイルを形成して取り組んでいかれることをおすすめします。