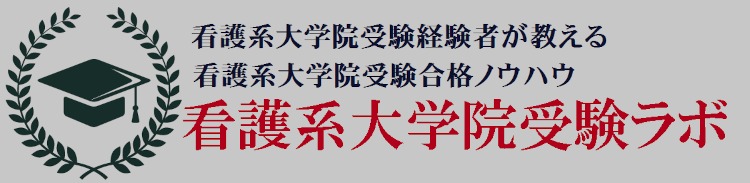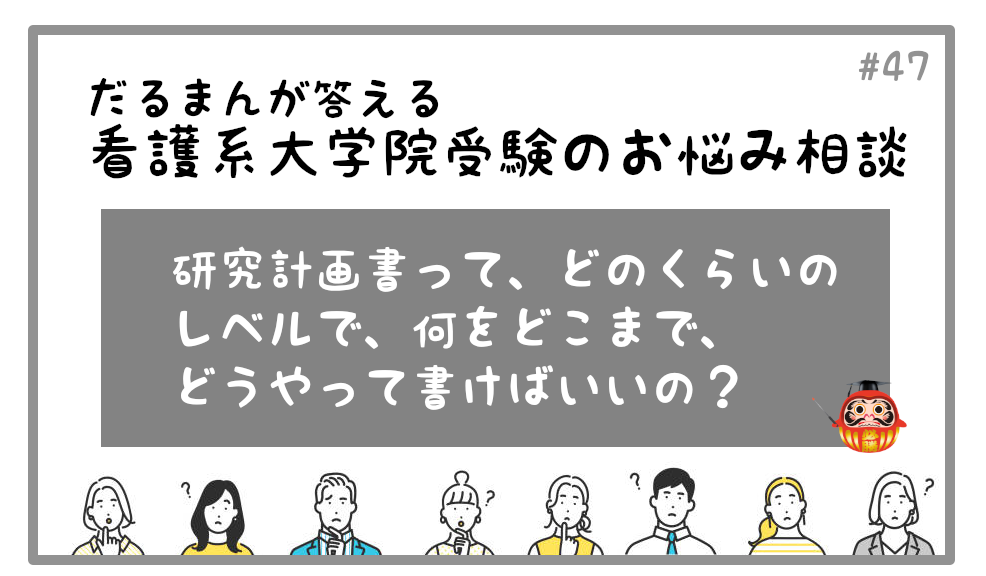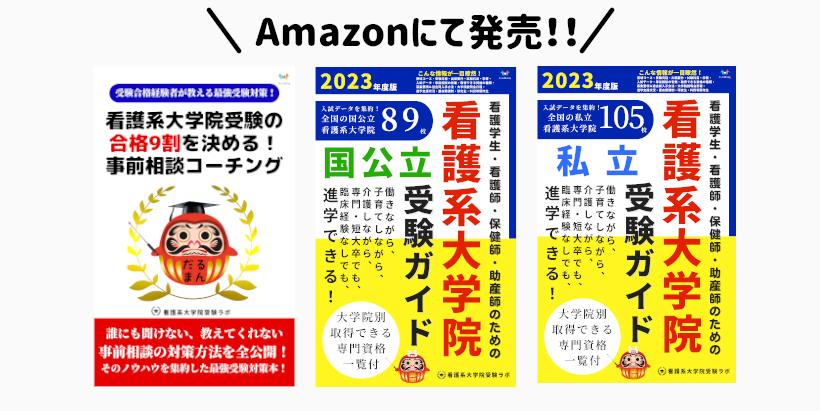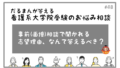こんにちは、だるまんです。
大学院受験の出願書類の一つに研究計画書があります。
研究計画書の書き方に決まりはないので、どのくらいのレベルを求められているのか、どこまで書くべきなのか、そもそも、どうやって書いたらいいのか…等など、わからないことは多いものです。
そこで、今回は、研究計画書にどのくらいのレベルで、何をどこまで、どうやって書けばいいのかについて、お話しします。
質問内容

大学院受験の出願書類に研究計画書があるのですが、どうやって書いたらいいのかがわかりません。書いたとしてもそれが受験にふさわしいレベルであるかを知る基準があれば教えて下さい。
だるまんの回答
どのくらいのレベルか
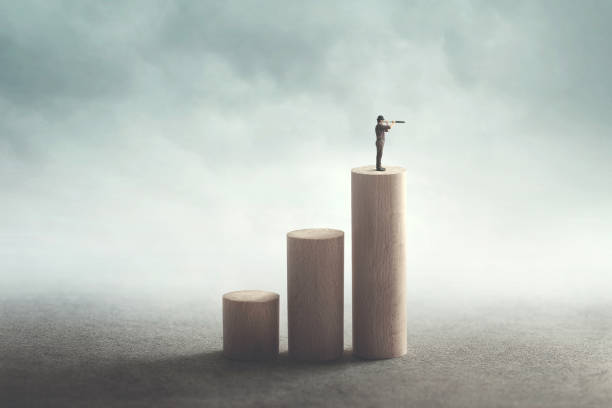
まず、大学院受験の出願書類として提出する研究計画書なので、それ相当のレベルの高い研究計画書が求められているかと言うと、そうでもない、と言えます。
もちろん、研究計画書を書いたご経験があり、それなりに書けるなら何よりですが、大学院進学希望者の大半は看護研究をした経験が多くない方です。
それは大学の教授も把握されており、高いレベルの研究計画書を求めているわけではないと思います。
ではどこを目指したらいいのかというと、誰が読んでも、言ってしまえば看護に関係ない他人が読んでわかる程度で構わず、強いて言うならば、順序良くストーリー展開が出来ているかどうかレベルです。
文章の構成や文章力、専門性の高さ等は、進学後に修正していく部分であり、受験時に見られていることは、基本的に文章が順序良く書けているか程度で、それより肝心なことは「研究テーマ」です。
なぜなら、あなたがどうしてその研究テーマに関心を持ったのか、その視点のほうが研究者として気になることだからです。
要は、国立大学であっても、レベルは気にせず、ビビる必要は全くない、ということです。
その時間なら、研究テーマを磨くべしです。
何をどこまで書いたらいいか

では、レベルは気にしなくてよいことがわかったところで、次に、何をどこまで書いたらよいのでしょうか。
一般的な研究計画書と言うと、
- 研究の背景
- 研究目的
- 研究方法
- 研究対象
- 研究結果で明らかになること(期待される成果)
という内容で構成されるものですが、大学院受験の研究計画書で必要な部分は、
- 研究の背景
- 研究目的
の2点のみです。
これで、かなり負荷が減ったと思いませんか?
もっと簡単に言い換えれば、「なぜその研究をしようと思ったのですか?」です。
なので、難しく考えることはなく、誰かに聞かれたら答えられるセリフを、文章化して、必要あらば統計の数値や他文献などを引用して、整えていくことで、誰でも研究計画書は作ることができます。
どうやって書いたらいいか

では、いよいよ、肝心なこと、どうやって書けばいいの?という疑問ですが、その疑問を解くために、下記に2つの記事を用意しています。
具体的には、
「現在、どのような研究の背景(現場の状況)があり、そこにはどのような問題があり、その問題に対してどのような研究はされている一方で、どのような研究はされておらず、そこについてこの研究を持って明らかにしたい」
というアウトラインに沿って、自分の言葉と、必要な資料や専門用語、データを探して、それらを文字化して入れ込んでいく、まるでパズルのような作業になります。
この記事2つで、具体的な例を用いた書き方例を提示していますので、ぜひ参考にしていただき、ご自分のオリジナル研究計画書を作って頂ければと思います。
まとめ
以上、「研究計画書にどのくらいのレベルで、何をどこまで、どうやって書けばいいのかについて」でした。
研究計画書は審査書類の一つであるので、手を抜けない書類ではありますが、受験だからではなく、これから大学院で取り組んでいく研究内容であるからこそ、何を聞かれても答えられるほどの知識と情報はしっかり蓄えておくべきです。
受験勉強で忙しい時期だとは思いますが、いずれば面接対策に繋がっていくことですので、試験対策のひとつとして、準備していきましょう。
日々、一日一日の小さな努力の積み重ねが、あなたが望む未来に繋がっていることを知ることです。